登山者はこうして遭難する:カテゴリー
山中での病気の悪化
登山中は遠慮呵責のない自然の外気にさられれる訳ですから、持病を持つ人は注意していくべきです。特に標高2400メートルを超える山では、高山病の症状(頭痛、息切れ、運動能力の低下など)が現れます。中高年登山者の方で、高血圧等の持病のある方が、高山を登山中に倒れたり、行動不能となるケースが目立っています。
もし持病を持っているのであれば、入山前に病院等で診察を受けるか医師に相談する等、特に中高年の方は登山の際には体調管理を万全にするべきです。
長野県警山岳遭難救助隊が発表した平成20年度の夏山(7月~8月)の事故統計によると、登山中の病気が原因で遭難する人が、全体の15,5%。1位:転落・滑落(29,5%)、2位:転倒(28.6%)についで3位になっています。
2009年8月8日にも、槍ヶ岳を登山中の66歳の男性が登山中に突然倒れて死亡するという遭難事故が起きています。
また、夏山では熱中症(日射病・熱射病)による遭難事故も、非常に多くなっています。熱中症の対処法は、別項をご覧ください。
もし持病を持っているのであれば、入山前に病院等で診察を受けるか医師に相談する等、特に中高年の方は登山の際には体調管理を万全にするべきです。
長野県警山岳遭難救助隊が発表した平成20年度の夏山(7月~8月)の事故統計によると、登山中の病気が原因で遭難する人が、全体の15,5%。1位:転落・滑落(29,5%)、2位:転倒(28.6%)についで3位になっています。
2009年8月8日にも、槍ヶ岳を登山中の66歳の男性が登山中に突然倒れて死亡するという遭難事故が起きています。
また、夏山では熱中症(日射病・熱射病)による遭難事故も、非常に多くなっています。熱中症の対処法は、別項をご覧ください。
読図技術の不足
中高年登山に限らず、山を登るときには老若男女・地図とコンパスは必携です(地図を持たなかったための遭難例)。
しかし、もし地図を持っていたとしても、そこから情報を見出す「読図技術」がなければ、せっかくの地図も意味を持ちません。この項では、読図技術の不足から遭難に至った事例を見てみましょう。
場所:富山県大品山
時期:3月下旬
メンバー:53~68歳の男性5人、女性2人。
行動概要:
詳しい遭難報告はこちら
http://homepage1.nifty.com/toyamaHC/aebs27.html
この山行はハイキングクラブの読図訓練山行だったそうですが、道に迷い遭難してしまうという皮肉な結果になってしまいました。全員無事救助されたのは、不幸中の幸いでした。
この遭難に際してのパーティーリーダーのコメントに、「他の登山者の足跡を深追いし過ぎ、本来通るつもりだった尾根よりひとつ手前の尾根を下ってしまった」という言葉があります。
トレースを深追いしてしまうというのは道迷い遭難の典型ですが、「おかしい」と感じた時点で地図を開き現在地確認をするのは、基本中の基本。なにより、この山行は「読図訓練」だったわけですから・・・。
決定的なのは、赤字の「次第に斜面が急になり始め、ロープを出して下らなければならない所もでてきた」ところ。この時点でルートを誤ったことがほぼ決定的になったわけですから、地形図を広げて現在地確認すべきだったはずです。しかもGPSまで持っていた(もっとも文面から察するに、リーダーではなくメンバー個人の持ち物だったようです)のですから・・・。
そして、ルートを誤ったことを確認したら、とにかく今まで来た道を登りかえす。もし登り返しの道すらわからなくなってしまったら、その場でビバーク。これが道迷い遭難時の基本です。闇雲に歩き回り体力を消耗させてはいけません。
ただ遭難報告書の文面からだけではわかりませんが、あるいは地図で現在地確認をしていた可能性も否定はできません。もしそうであれば、樹林帯で地形が見渡せず地形把握が難しかったであろうことを差し引いても、読図技術が未熟だった、というしかないでしょう・・・。
二万五千分の一地形図を読みこなす技術は、ハイキング以上の登山をする全てに登山者に必須の技術です。しっかり勉強しましょう。
山岳地形と読図 (ヤマケイ・テクニカルブック 登山技術全書)
(お勧めの一冊。地図と現場のカラー写真が対比されていて、非常にわかりやすく読図を勉強できます)
しかし、もし地図を持っていたとしても、そこから情報を見出す「読図技術」がなければ、せっかくの地図も意味を持ちません。この項では、読図技術の不足から遭難に至った事例を見てみましょう。
場所:富山県大品山
時期:3月下旬
メンバー:53~68歳の男性5人、女性2人。
行動概要:
| 3 月 21 日 |
(快晴) 大品山山頂を出発。トップのサブリーダがトレースに導かれてルートを誤り、登山道から外れた尾根を下ってしまう。この時、別のメンバーがコース取りに疑問を呈する(地図、GPSで確認)。 次第に斜面が急になり始め、ロープを出して下らなければならない所もでてくる。2~3度かなり厳しい下降をロープフィッ クスでやった後、ビバーク(不時露営)地点となる崖に遭遇。20~30m下方に林道らしき地形が確認できたが、陽がかげってきて薄暗くなっていること、ロープをフィックスする支点および足場の確保が難しいことなどを考え下降をあきらめ、より安全な場所への登り返しも不可能と判断しビバークを決定。 携帯電話が通じたので、クラブのメンバーの自宅に連絡、110番経由で富山県山岳警備隊へも事態と現在位置を知らせる。山岳警備隊から「現在位置動かず一晩がんばれ!明日早朝ヘリを出動させ、救出に向かう」との連絡を受ける。 |
3 月 22 日 |
富山県消防防災ヘリにより全員ピックアップされ、ゴンドラリフト駐車場へ搬送される。 |
詳しい遭難報告はこちら
http://homepage1.nifty.com/toyamaHC/aebs27.html
この山行はハイキングクラブの読図訓練山行だったそうですが、道に迷い遭難してしまうという皮肉な結果になってしまいました。全員無事救助されたのは、不幸中の幸いでした。
この遭難に際してのパーティーリーダーのコメントに、「他の登山者の足跡を深追いし過ぎ、本来通るつもりだった尾根よりひとつ手前の尾根を下ってしまった」という言葉があります。
トレースを深追いしてしまうというのは道迷い遭難の典型ですが、「おかしい」と感じた時点で地図を開き現在地確認をするのは、基本中の基本。なにより、この山行は「読図訓練」だったわけですから・・・。
決定的なのは、赤字の「次第に斜面が急になり始め、ロープを出して下らなければならない所もでてきた」ところ。この時点でルートを誤ったことがほぼ決定的になったわけですから、地形図を広げて現在地確認すべきだったはずです。しかもGPSまで持っていた(もっとも文面から察するに、リーダーではなくメンバー個人の持ち物だったようです)のですから・・・。
そして、ルートを誤ったことを確認したら、とにかく今まで来た道を登りかえす。もし登り返しの道すらわからなくなってしまったら、その場でビバーク。これが道迷い遭難時の基本です。闇雲に歩き回り体力を消耗させてはいけません。
ただ遭難報告書の文面からだけではわかりませんが、あるいは地図で現在地確認をしていた可能性も否定はできません。もしそうであれば、樹林帯で地形が見渡せず地形把握が難しかったであろうことを差し引いても、読図技術が未熟だった、というしかないでしょう・・・。
二万五千分の一地形図を読みこなす技術は、ハイキング以上の登山をする全てに登山者に必須の技術です。しっかり勉強しましょう。
山岳地形と読図 (ヤマケイ・テクニカルブック 登山技術全書)
(お勧めの一冊。地図と現場のカラー写真が対比されていて、非常にわかりやすく読図を勉強できます)
体力不足による遭難:北海道トムラウシ山
体力には、行動体力と防衛体力の2つの種類があります。
行動体力は、私達が一般的に「体力」として認識しているもので、重い荷物を担いで長時間歩ける、といったことが「行動体力がある」ということになります。
もう一つの「防衛体力」ですが、これは簡単に言えば「体調を維持するための力」で、「雨にぬれても体調を崩さない」といったことがこの防衛体力にあたります。
中高年になるとこの2つの体力がともに衰えてきますが、「防衛体力」の衰えは特に気付きにくいものなので、注意が必要です。
この項では、体力不足(行動・防衛両体力を含む)が原因で遭難に至った、北海道大雪山系トムラウシ山の遭難事故をみてみましょう。
 場所:北海道大雪山系トムラウシ山
場所:北海道大雪山系トムラウシ山
時期:7月初旬
メンバー:4人パーティー
(遭難者はリーダー格の方)
行動概要:
詳しい遭難状況はこちらから
http://www.ne.jp/asahi/slowly-hike/daisetsuzan/02taisetudata/04sonanjiko/20020711-13tomuraushi.html
この遭難から得られる教訓
登山の計画を立てる際は、パーティーの体力(=一番弱い人の体力)に合わせて計画をたてるべきです。
この場合「行動体力」にばかり目が向けられがちですが、「防衛体力」も考慮に入れるべきです。もし睡眠不足の状況でも踏破できるか、体調が悪くなっても行動しきれる範囲か、そして天候が最悪の状況になっても自分の体力で下山しきれるか・・・。非常時になればなるほど、外科医が患者を見るような冷静な目で自分の、そしてメンバーの体調をチェックする必要があります。
遭難報告を見ると、相当歩くペースが遅かったことがうかがえ、計画に甘さがあったことがうかがえます。
7月11日の「トムラウシ山を巻いて下山する」という判断は、
・台風の北海道接近は翌日らしい
・天候回復の見通しが無い
・長引くと食料が足りない
・他のパーティの多くが下山開始
という点から見て、通常なら決して間違えと言える選択ではありません。ビバーク装備も持っていたとのことですし・・・。しかし「その行程を悪天候の中歩ききる体力が、その時点で残っていなかったことを自覚できなかった」ことが、最悪の事態に至った要因の一つと言えるでしょう。
ルートの性質上、進むか停滞するかの選択肢しかありませんでした。自分達の体力を客観的に把握できていれば、停滞という道を選択する(1~2日は何も食べないことになるにしても・・・)ことができたのではないでしょうか。
行動体力は、私達が一般的に「体力」として認識しているもので、重い荷物を担いで長時間歩ける、といったことが「行動体力がある」ということになります。
もう一つの「防衛体力」ですが、これは簡単に言えば「体調を維持するための力」で、「雨にぬれても体調を崩さない」といったことがこの防衛体力にあたります。
中高年になるとこの2つの体力がともに衰えてきますが、「防衛体力」の衰えは特に気付きにくいものなので、注意が必要です。
この項では、体力不足(行動・防衛両体力を含む)が原因で遭難に至った、北海道大雪山系トムラウシ山の遭難事故をみてみましょう。
 場所:北海道大雪山系トムラウシ山
場所:北海道大雪山系トムラウシ山時期:7月初旬
メンバー:4人パーティー
(遭難者はリーダー格の方)
行動概要:
| 7月8日 | 旭岳温泉宿泊 |
| 7月9日 | (曇り時々晴れ) 4人パーティーで入山。白雲岳非難小屋泊。 標準コースタイム7時間あまりの行程に10時間を要している。 非難小屋が混雑していたため睡眠不足になる。 |
| 7月10日 | (薄曇のち、夕方から風雨が強くなる) ヒサゴ沼非難小屋泊。 標準コースタイム8時間あまりの行程に11時間以上を要している。 |
| 7月11日 | (風雨強し) 悪天候の中出発。トムラウシ岳山頂を巻いて下山する予定が、コースを間違え登頂してしまう。山頂から南沼キャンプ地への下りで、リーダー格の女性(以下遭難者)が転倒し負傷。転倒する前から、体調は既に悪化していたらしい。ここで遭難者は行動不能に。付き添い一人を残し、2人が下山。2人はビバーク。 *下山した2人も結局下りきれず、途中ビバーク。 |
| 7月12日 | (雨) 先に下山した2人が、登山口にたどり着く。付き添いの1人も下山、遭難者は死亡。 |
| 7月13日 | (曇時々雨) 遭難者をヘリで病院搬送、死亡確認。 |
詳しい遭難状況はこちらから
http://www.ne.jp/asahi/slowly-hike/daisetsuzan/02taisetudata/04sonanjiko/20020711-13tomuraushi.html
この遭難から得られる教訓
登山の計画を立てる際は、パーティーの体力(=一番弱い人の体力)に合わせて計画をたてるべきです。
この場合「行動体力」にばかり目が向けられがちですが、「防衛体力」も考慮に入れるべきです。もし睡眠不足の状況でも踏破できるか、体調が悪くなっても行動しきれる範囲か、そして天候が最悪の状況になっても自分の体力で下山しきれるか・・・。非常時になればなるほど、外科医が患者を見るような冷静な目で自分の、そしてメンバーの体調をチェックする必要があります。
遭難報告を見ると、相当歩くペースが遅かったことがうかがえ、計画に甘さがあったことがうかがえます。
7月11日の「トムラウシ山を巻いて下山する」という判断は、
・台風の北海道接近は翌日らしい
・天候回復の見通しが無い
・長引くと食料が足りない
・他のパーティの多くが下山開始
という点から見て、通常なら決して間違えと言える選択ではありません。ビバーク装備も持っていたとのことですし・・・。しかし「その行程を悪天候の中歩ききる体力が、その時点で残っていなかったことを自覚できなかった」ことが、最悪の事態に至った要因の一つと言えるでしょう。
ルートの性質上、進むか停滞するかの選択肢しかありませんでした。自分達の体力を客観的に把握できていれば、停滞という道を選択する(1~2日は何も食べないことになるにしても・・・)ことができたのではないでしょうか。
装備の不備(地図を持たない):宮崎県時雨岳
登山に2万5千分の1地形図(入山者の多いポピュラーな低山なら、5万分の1地図も許容範囲)とコンパスを持っていくのは常識中の常識。何かの拍子にルートをはずし道に迷っても、現在地確認ができれば、恐れることはありません。また、登山をするに際しては、国土地理院の2万5千分の1地形図を読みこなせるだけの、『読図力』は必須の能力です。
この項では、ヒマラヤ遠征や冬の北アルプス登山など40年以上の経験を持つ山のベテランが、駐車場からたった1時間で山頂の山に地図を持たずに入山してしまい、道に迷った末に5日目に救助された例を見てみましょう。
場所:宮崎県時雨岳
時期:5月中旬
行動概要:
詳しい遭難報告はこちら
http://www.gsoq97.com/miyasanngaku.html
遭難に至った根本的な原因は、やはり地形図とコンパスを持っていなかったことでしょう。登山の大ベテランの方ですから、この2つがあれば、この状況で遭難することはまず考えられません。
この遭難から得られる教訓
たとえ低山であっても、何かの拍子にコースを見失い、道に迷ってしまうことはありえます。そんな時生死を分けるのが地形図とコンパス、そして読図技術です。
しかし遭難という結果になってしまいましたが、さすが山のベテランだけあって、かなり冷静な判断をしています。
『沢からはザアザアと水は大量に流れているのですが、どの沢も急坂で下りると尾根に戻る体力がない。それなら体力を温存する方を選んだほうが生き延びられると判断した』
『時間はまだ3時、後4時間はあるいてもよいが、そのとき雨宿りする銘木がなかったら、其れは死を意味する。』
『屋根のないところで、雨に打たれたらお仕舞、無駄な体力の浪費は凍死に繋がる。先人の教訓を胸にたたんで、慌てることがなかったのがよかったと思います。』
など、行動ができなくなった場合の大原則、『その場でビバークも覚悟の上で、天候の回復を待つ。パニックになって動き回り、体力を消耗させないこと』を実践しています。
この項では、ヒマラヤ遠征や冬の北アルプス登山など40年以上の経験を持つ山のベテランが、駐車場からたった1時間で山頂の山に地図を持たずに入山してしまい、道に迷った末に5日目に救助された例を見てみましょう。
場所:宮崎県時雨岳
時期:5月中旬
行動概要:
| 5月11日 | (雨のち曇り) 単独で入山。写真撮影に熱中するうちに方向を失い、ビバーク。 |
| 5月12日 | (曇り) 道を探し行動するも、発見できず。家族が騒ぎ出し、身内での捜索開始。 |
| 5月13日 | (曇りのち夜半から雨) 家族から警察に正式に捜索願が出される。遭難者本人は、大きな倒木の隙間に葉っぱを敷き詰め天候の回復を待つ。捜索隊は手がかりを発見できず。 |
| 5月14日 | (快晴。山中は霧のち晴) 捜索するも手がかりなし。遭難者本人は、前日と同じ場所で、大きな倒木の隙間に葉っぱを敷き詰め天候の回復を待つ。 午後天候が回復したので、行動開始。沢で行き詰まり、そこでビバーク。 |
| 5月15日 | (晴れ) 身内の捜索で車を発見、遭難現場がはじめて特定される。同時に救助隊が捜索を開始。 遭難者は行動(登高)を開始し、10時間の歩行の後林道に自力で脱出。午後6時、車が発見されたところからは40km離れた地点で森林組合の人に発見され、救助される。 |
詳しい遭難報告はこちら
http://www.gsoq97.com/miyasanngaku.html
遭難に至った根本的な原因は、やはり地形図とコンパスを持っていなかったことでしょう。登山の大ベテランの方ですから、この2つがあれば、この状況で遭難することはまず考えられません。
この遭難から得られる教訓
たとえ低山であっても、何かの拍子にコースを見失い、道に迷ってしまうことはありえます。そんな時生死を分けるのが地形図とコンパス、そして読図技術です。
しかし遭難という結果になってしまいましたが、さすが山のベテランだけあって、かなり冷静な判断をしています。
『沢からはザアザアと水は大量に流れているのですが、どの沢も急坂で下りると尾根に戻る体力がない。それなら体力を温存する方を選んだほうが生き延びられると判断した』
『時間はまだ3時、後4時間はあるいてもよいが、そのとき雨宿りする銘木がなかったら、其れは死を意味する。』
『屋根のないところで、雨に打たれたらお仕舞、無駄な体力の浪費は凍死に繋がる。先人の教訓を胸にたたんで、慌てることがなかったのがよかったと思います。』
など、行動ができなくなった場合の大原則、『その場でビバークも覚悟の上で、天候の回復を待つ。パニックになって動き回り、体力を消耗させないこと』を実践しています。
気象遭難(濃霧):前大日岳での事故事例
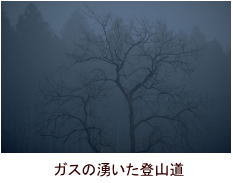 山では時として、下界では信じられないほど濃いガス(霧)に巻かれることがあります。経験しないとわからないでしょうが、自分の靴さえはっきり見えないほどの濃霧です。
山では時として、下界では信じられないほど濃いガス(霧)に巻かれることがあります。経験しないとわからないでしょうが、自分の靴さえはっきり見えないほどの濃霧です。
このように、悪天候が原因で行動ができなくなった場合の大原則は、その場でビバークも覚悟の上で、天候の回復を待つこと、です。
それではここで、濃霧で視界が効かない中を闇雲に動き回ってしまったために、遭難してしまった例を見てみましょう。
場所:北アルプス前衛峰・前大日岳(富山県)
時期:5月の連休
行動概要:
| 4月27日 | 単独日帰りの予定で入山。 8時48分、早乙女岳登頂。視界良好。 9時50分、前大日岳登頂。直前からガスが出始める。 10時、下山開始。直後から足元も見えないほどのガスに包まれる。パニック状態の中で、闇雲に下山するが、完全に道を失い、戻るのが不可能な谷に降り立ってしまう。 4時半ごろ、沢を下る中で、流される。奇跡的に雪渓の上に這い上がり、ビバーク。 |
| 4月28日 | 5時半ごろ、ヘリ救助を期待し、右岸の山に登高。ヘリのホバーリングが可能な地点まで登る。 9時20分ごろ:県警ヘリにて救助 |
詳しい遭難報告はこちら
http://www.ctt.ne.jp/~jijii/020427sounan.htm
全身ずぶ濡れ、食料もビバーク装具もなし(携行はしていたが、沢で流され紛失)の5月の山でビバークし助かったのは、奇跡に近いものがあります(詳細は上記遭難報告書をご覧ください)。
遭難に至る原因はいろいろありますが、根本的に、「悪天候が原因で行動ができなくなった場合は、その場でビバークも覚悟の上で、天候の回復を待つ」という原則を守れば防げたであろう事故です。ガスに巻かれ行動不能になったその場でビバークしていれば、命に危険が及ぶことはなかった可能性が高いです。
パニック状態になり、闇雲に行動(下山)してしまったがゆえに、助かったことが奇跡とも言えるビバークをすることになってしまいました。
~この遭難から得られる教訓~
遭難報告書の文面から、遭難された方はかなり豊富な登山の経験があることが伺えます。しかしその経験豊富なベテランにして、パニック状態になると適切な判断ができなくなることがわかります。遭難を自覚したときの大原則は、『パニックにならない。また、パニック状態になっていると少しでも自覚したら、その場で己の行動を禁止すること』です。実はこれこそが、『言うは易し、行なうは難し』なのですが・・・。
また、奇跡的に助かった要因を考察してみます。
1.留守宅に登山計画を残していた。結果として、捜索が効率的に行われた。
2.装備がしっかりしていた。途中沢でザックを流されてしまったが、もしピッケルがなければ、沢から這い上がることができず、死んでいた可能性が大。
3.速乾性の新素材の下着を着ていた。これがなければ、ビバークで凍死していたと思われる。
4.山の知識がかなりあった。現在地を推測したり、テープの場所まで登り返したり、食べられそうな草花を見分けたりと、パニック状態にしてはかなり冷静な判断をしていた。豊富な経験が伺える。
5.遭難初期に、「道に迷ったようだ」と携帯電話で家に連絡している。このおかげで、捜索の初動が早かった。
6.ビバーク翌日、冷静に自分の体の状態を分析し、ヘリ救助を受けるために全力を傾けている。もし無理をして行動して(下って)いれば、死んでいた可能性大。
最後に。
止まない雨はない、晴れないガスはない。雨が止むまで、霧が晴れるまで待つ!たとえ下山が遅れ多少の迷惑をかけようとも、死んでしまうよりはずっとましです。
Page:
1
